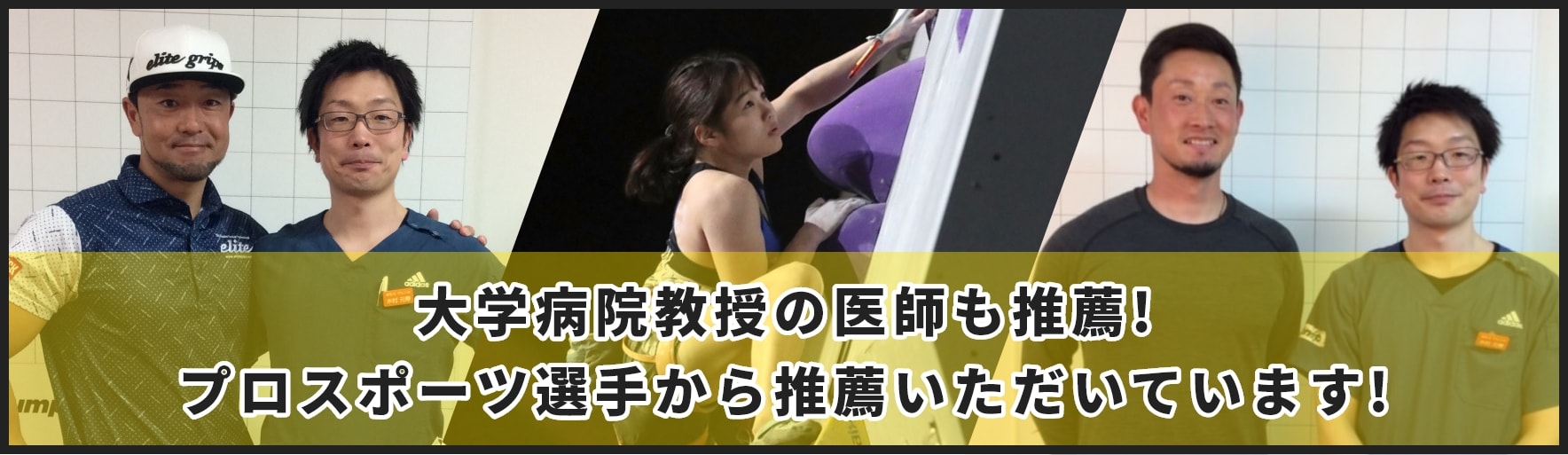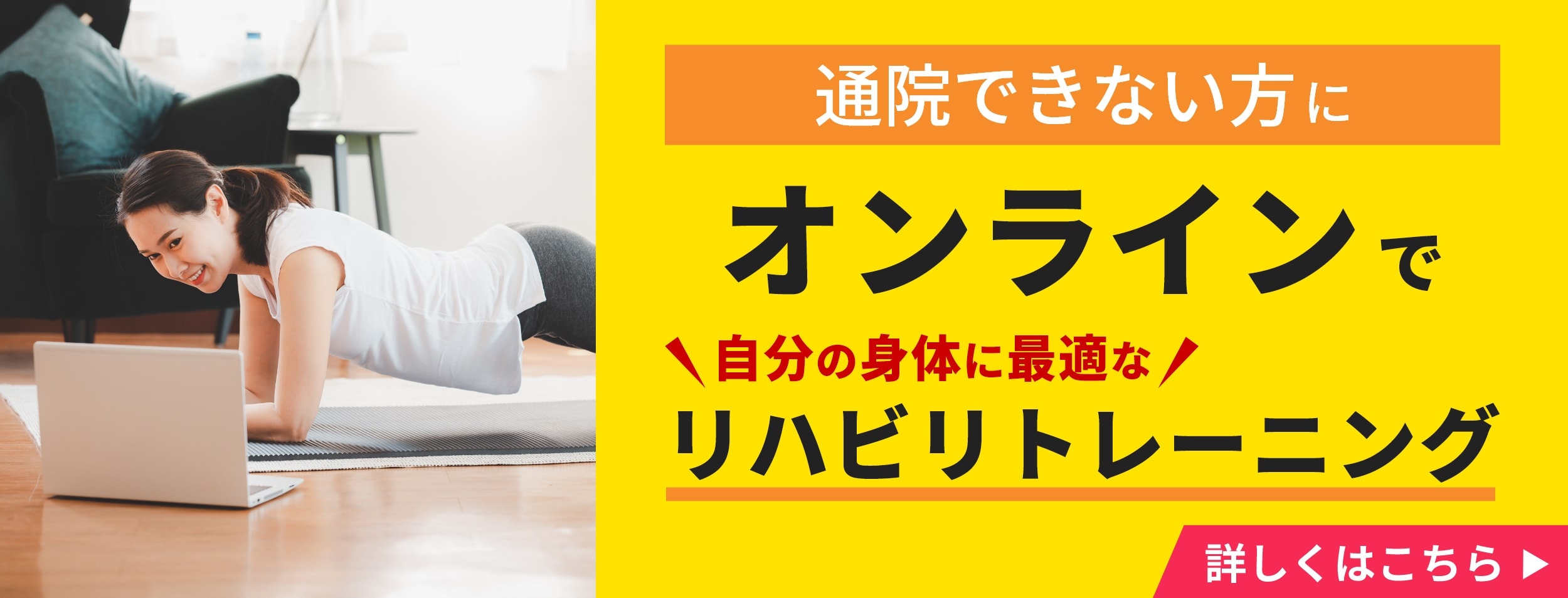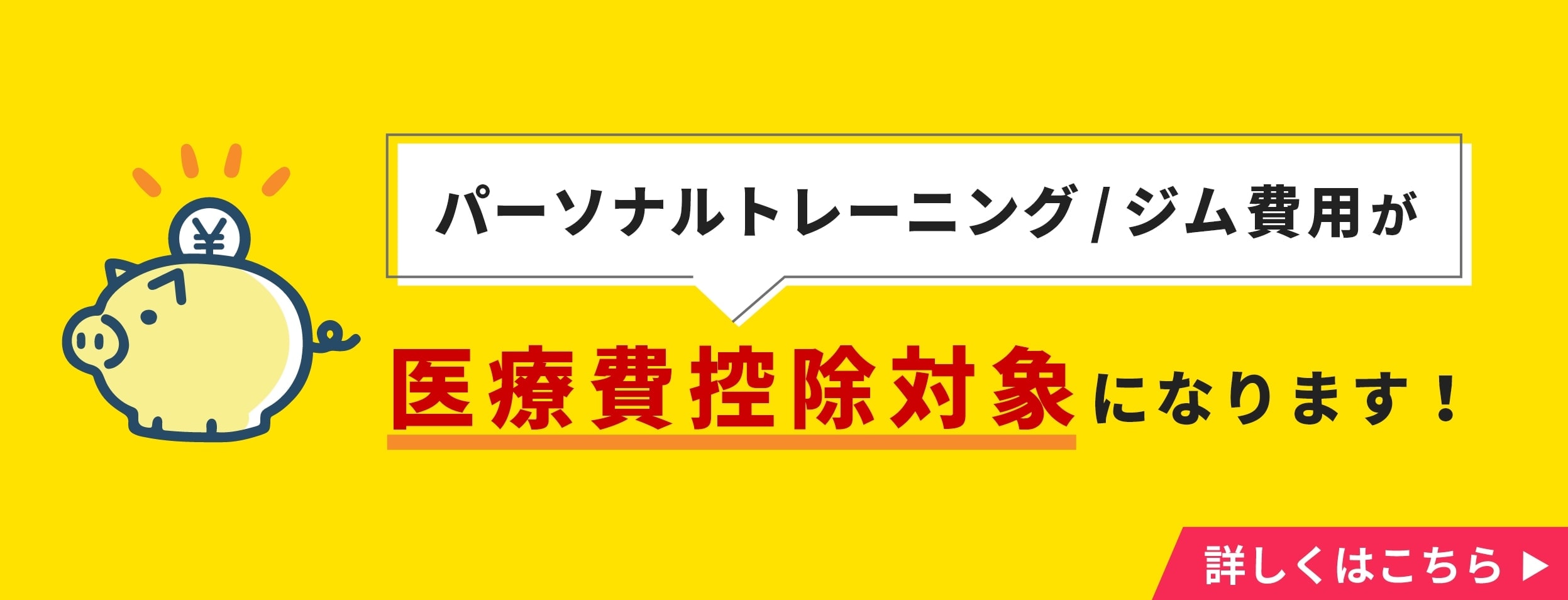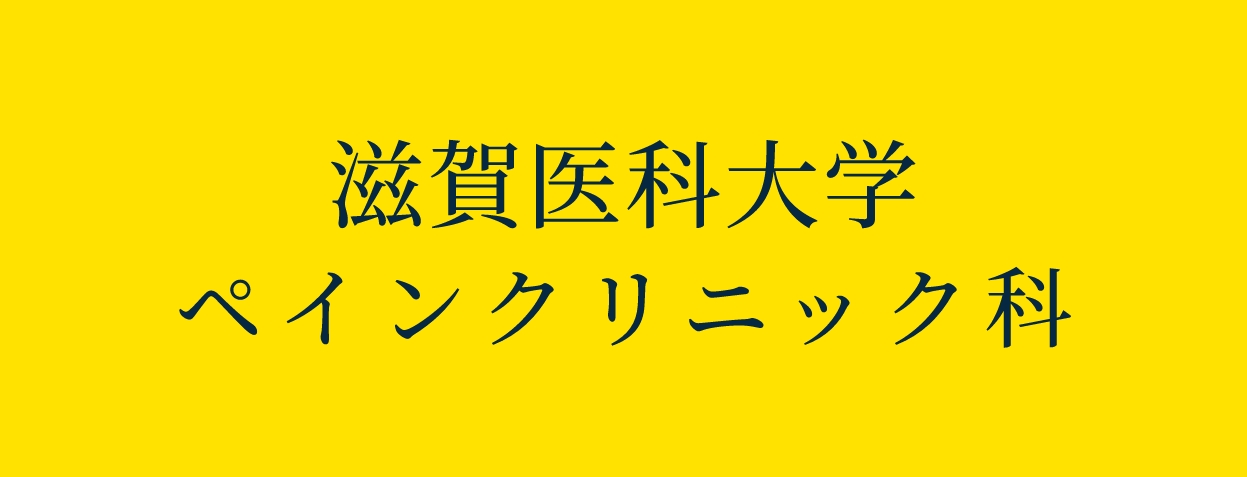草津市南草津【理学療法士がしっかり診る整体院】Jumpです。

「梅雨時になるとなぜか腰痛がひどくなる」とか「毎年この季節になるとぎっくり腰になる」などと言う方は結構たくさんいるようです。ではなぜ梅雨時になると腰痛の人が増えるのでしょうか。
今回は梅雨時に腰痛が出るメカニズムについて解説するとともに、腰痛の意外な原因と対処法について紹介したいと思います。
1.梅雨時に腰痛が出やすい理由

それでは早速ですが、梅雨時に腰痛が出やすい理由について見ていきたいと思います。梅雨時に腰痛が出る理由としては、気圧や気温の変化、汗による冷えといったことがあげられます。
1-1.気圧の変化
雨が降る前になると頭痛が出るとか、台風が来る前になると関節痛が出るなどと言うことは、経験則としてよく知られていましたが、現在では医学の世界でも気圧が痛みに関与することが定説となっています。
医学の中でも気象医学という分野では、気圧と痛みとの関係について研究を重ねており、その結果、気圧がさがると痛みが出やすいことが分かってきています。名古屋大学で行われた実験に次のようなものがあります。
手の痛みや頭痛を持っている人に気圧を上下できる実験装置に入ってもらい、10分ほどかけて気圧を30ヘクトパスカル下げ、その状態を15分継続、その後10分かけて元の気圧に戻しました。
すると、気圧がさがりはじめると同時に手の痛みが増し、気圧が元に戻ると痛みが和らいだということです。頭痛に関しは、気圧が戻ってからも続いたということです。
つまり、気圧がさがることによって、症状が悪化することが分かったのです。人間の場合には先入観もあるため、実験用のラットを用いて同様の実験がおこなわれました。
その結果、ラットの場合も気圧がさがると痛みを強く感じることがわかったのです。さらに交感神経を切ったラットで実験をおこなったところ、気圧が変化しても影響はなかったということです。
このことから、気圧による痛みの変化には交感神経が関与していることも分かったのです。話をまとめると、気圧がさがると交感神経が優位になり、結果として痛みを感じやすくなるということです。
1-2.気温の変化
気温の変化も梅雨時に腰痛が出やすくなる原因の1つです。梅雨時には蒸し暑くなり気温も上昇します。一方、電車内やバス、スーパーなどは冷房で冷えています。
梅雨時の濡れた身体がエアコンの風にさらされることで、冬よりもかえって芯から冷えてしまうのです。ま気温が高くなってくると冷たい飲み物を飲む機会も増えてきます。
腰痛の原因の1つとして腸腰筋の緊張があげられますが、エアコンと冷たい飲み物で外と内から腸腰筋を冷やしてしまうため、腰痛のリスクが高くなるのです。
1-3.汗による冷え
汗をかくと乾くときに気化熱で体表から熱を奪います。この機能はホメオスタシス(恒常性)の一種で、体温を一定に保つために重要な機能となっています。
ただ、現代では先にも述べたようにエアコンがどこでも備えられているため、汗が乾くときに身体を冷やし過ぎでしまうのです。そのことも梅雨時に腰痛が増える一因となっています。
2.腰痛の本当の原因

腰痛を訴えて病院や整形外科を受診した人の中には、レントゲンやMRIを撮った結果「異常なし」と言われた人も多いと思います。実際に腰痛の85%は原因不明とされますが、なぜそのようなことが起こるのでしょうか。
それは病院や整形外科では腰の骨や神経しか診ていない場合が多いからです。
そこで筋肉や身体の使い方に関するプロフェッショナルの観点から、腰痛の本当の原因に迫りたいと思います。
2-1.長時間の同一姿勢
腰痛は腹筋が足りないから起こるとか、筋力が不足しているから起こるなどと言われますが、実際には、それだけではありません。なぜなら、筋肉ムキムキのスポーツ選手にも腰痛持ちの人はたくさんいるからです。
昨今はデスクワークが主流となってきていますが、それにともなって腰痛持ちの人も増えているようです。デスクワークで同じ姿勢を長時間強いられると、腰痛の原因となる腸腰筋や腰部脊柱起立筋が緊張するためです。
腰痛には大きく分けて2のタイプあります。1つは筋肉の使いすぎによる腰痛で、もう1つが筋肉を使わなさすぎることによる腰痛です。そして、長時間の同一姿勢による腰痛は後者にあたります。
2-2.筋緊張
筋緊張は痛みと直結します。筋肉が緊張して硬くなると「筋疎血」が起こります。簡単に言うと筋緊張によって血管が圧迫され、血行が悪くなるということです。
筋疎血が起こると痛み物質が蓄えられ、それが筋肉痛のような症状を生むのです。その状態が続くと痛み物質がどんどん蓄えられ、慢性痛や急性痛につながるわけです。
2-3.筋膜など軟部組織の異常
日本には2800万人もの腰痛持ちの人がいますが、そのうちの85%は非特異的腰痛とされます。非特異的腰痛とは、検査をしても原因が分からない腰痛のことを意味します。
なぜそれほど多くの腰痛が原因不明とされるかと言うと、骨や神経しか診ていないからです。腰痛に限らず、痛みの出ている部分は「結果」でしかありません。
実際には周囲の筋肉や筋膜、腱や靭帯といった軟部組織の異常によって発症するケースがほとんどです。特に殿筋群や太ももの筋肉、首の筋肉とのつながりを見ることが、腰痛の根本的解決にとって重要です。
3.梅雨時の腰痛への対処法

梅雨時に腰痛が出やすい理由については分かりましたが、気圧をコントロールすることはできませんよね。では梅雨時に腰痛が出た場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
3-1.身体を温める
気圧がさがることによって交感神経が優位になると、血管が収縮して血流を阻害してしまいます。血流が悪くなると、局所の栄養状態が悪化し、痛みを誘発しやすくなります。
そのため、梅雨時には身体を温めることが重要です。特に寝る前にお風呂などで身体をしっかりと温めるとよいでしょう。その結果、副交感神経が優位になり、血流を促進することが可能となります。
3-2.適度な運動・ストレッチをする
梅雨時の腰痛への対処法としては、適度な運動やストレッチをすることもあげられます。特に有酸素運動(ウォーキングやサイクリングなど)は全身の血流が良くなり痛みが改善されやすいです。ただ、ウォーキングやサイクリングを痛みがある状態で無理をして行うと悪化させてしまう恐れがありますので、痛みがなく無理のない範囲で行うようにしましょう。また、ストレッチをすることで筋肉の血行を促進することが可能となります。
3-3.良質の睡眠をとる
良質の睡眠をとることも、梅雨時の腰痛への対処法となります。なぜなら、私たちの身体は寝ている間に修復されるからです。
睡眠中には成長ホルモンが分泌されます。成長ホルモンというと成長期に分泌されるものだと思われがちですが、実際には私たちが生きている間、ずっと分泌され続けます。
成長ホルモンの働きによって、私たちの身体は良好な状態を保てるのです。残念ながら成長ホルモンの分泌量は年々減少します。そのため、良質な睡眠を取ることがより重要となるのです。
また、成長ホルモンの分泌を促すためには食事に気をつける必要もあります。特に必須アミノ酸は成長ホルモンの分泌に関与しているので、積極的に摂取するよう心がけましょう。
4.まとめ
梅雨時に起こる腰痛は、その他の季節に起こる腰痛とは異なった特徴があります。それは気圧の変化によって痛みが出やすいということです。
日本人には欧米人とくらべて交感神経型が多いとされていることも、梅雨時に腰痛が増える一因となっているのかもしれません。梅雨時にはなるべくリラックスする時間を設け、腰痛が悪化しないようにしましょう。
草津市南草津【理学療法士がしっかり診る整体院】Jump(ジャンプ)の腰痛の施術・運動については症状別ページ「腰痛の施術・運動」のページをご覧ください。